25238S | 生物の「種」とは何かを考える
講座概要
| 講座番号 | 25238S |
|---|---|
| 開催日 | 2026/02/07(土)~2026/02/21(土) |
| 回数 | 全2回 |
| 定員 | 40 |
| カテゴリー | 趣味・教養 |
| 開講期 | 後期 |
| 時間 | 14:30~16:00 |
| 受付期間 | 2025/11/04~2026/01/27 |
| 受講料 | 5,000円 (学生:5,000円) |
| キャンパス | 世田谷キャンパス |
講座内容
生物の多様性は、動物約130万種、植物30万種といわれています。
そして、地球上にはさらに膨大な数の未記載種が生息していると考えらます。
我々はこの生物多様性を “種”というものを手がかりにして、250年以上にわたって理解してきました。
その結果、種に関する膨大な知識が蓄積されています。
このように、種は生物多様性の基本的単位と考えられてきました。
しかし、種をどのように理解したらよいか、という問題はいまだ十分に解決されていません。
種の概念は、いままでに20以上が提案されてきましたが、いずれの概念にも問題点があり
決定的なものは一つもありません。
つまり種をどのように捉えるかは、生物学上の難問中の難問なのです。
本講座では、今まで提案されてきた種概念の主なものを取り上げ、それらの優れた点と問題点について概説します。
そして結論として、種とは何なのかを、演者の見解も混えて解説します。
講義は、できるだけ具体的な例を取り上げて進めていきます。
そのために生物標本(世界のクモバチ、日本産全種のスズメバチやマルハナバチ、日本産マイマイカブリの全亜種、身近な野鳥の仮剥製標本など)を回覧して解説していきます。
また、種の名前(学名)の付け方や記載のし方などについても解説します。
これらを理解すれば、あなたも新種の記載ができるようになるかもしれません。
少なくとも種の記載の基本が理解できるようになるでしょう。
私たちの身の回りには、特に昆虫などの小動物のグループでいまだ多くの未知の種(未記載種=新種)が棲息していることを再確認していただこうと思います。
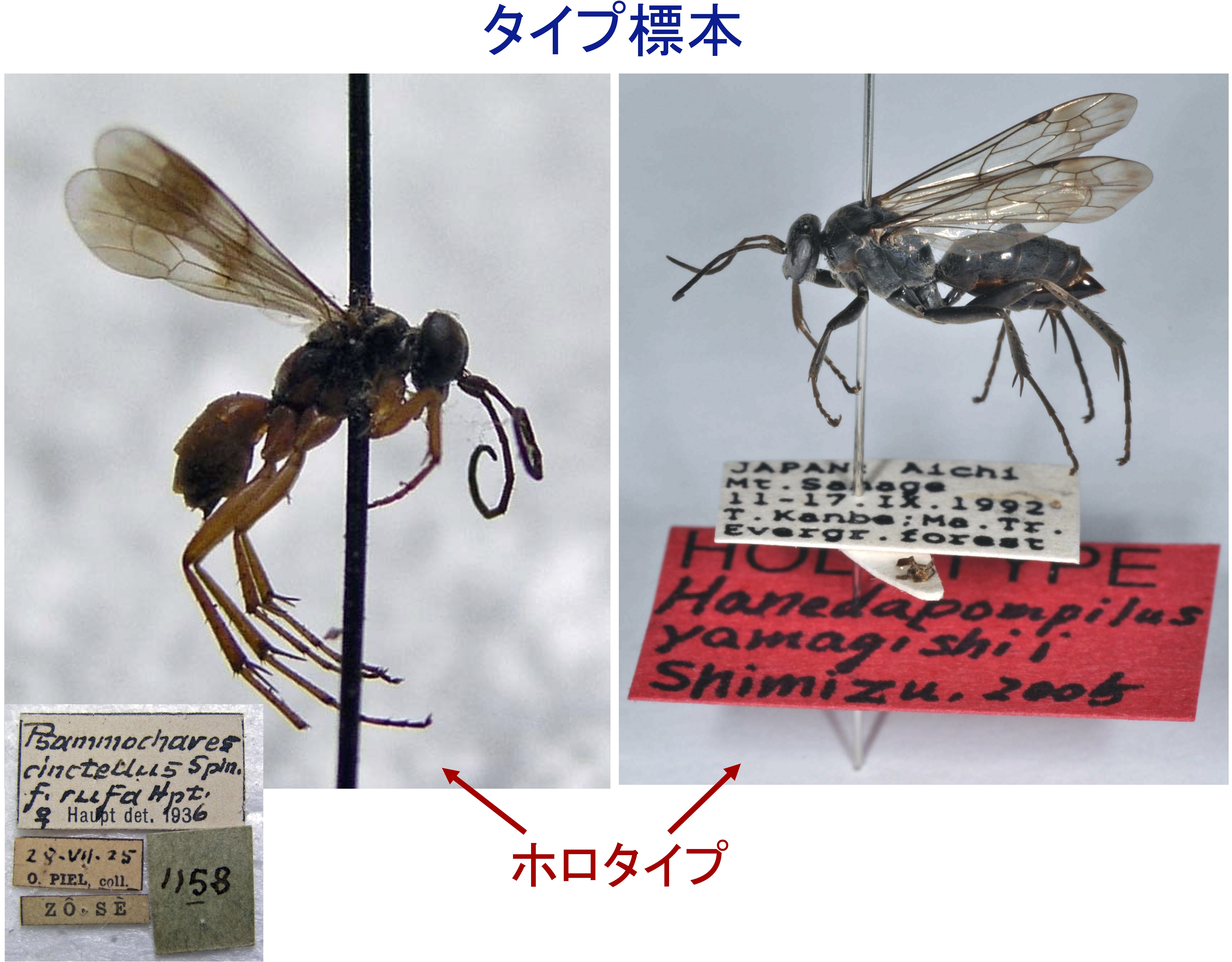
持ち物
筆記用具
対象
18歳以上
会場について
本講座の会場は、世田谷キャンパス(小田急線経堂駅または千歳船橋駅から徒歩20分)です。
教室の詳細は、マイページ(受講予定一覧)でご確認ください。
キャンパス内のアクセスは、マイページ(受講予定一覧⇒資料ダウンロード)より必ずご確認ください。
ハガキでお申込みの方には、別途ご案内いたします。
画像について
エルンスト・ヘッケル - Escaneado por L. Fdez. 2005-12-28, パブリック・ドメイン, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=483175による
講座スケジュール
| 回 | 実施日 | 講義内容 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/07 | 種の認識、学名、国際命名規約、分類体系 |
蝦名 元 清水 晃 |
| 2 | 2026/02/21 | 種とは何か、おもな種概念、種をどのようにとらえたらよいか |
蝦名 元 清水 晃 |
講師紹介
- 蝦名 元
- (一財)進化生物研究所研究員・学芸員・博士(環境共生学)
- 東京農業大学・東京農業大学稲花小学校非常勤講師
小中高・大学で講師を務め、博物館・科学館等で自然科学の楽しさや生きものをテーマとした講演・講座等のイベントを実施。テレビ等のメディアへの協力・監修も務める。
著書:『生きものラボ!子どもにできるおもしろ生物実験室』(講談社)、『群れ MURE 』(カンゼン、共著・監修)、『今を生きる古代型魚類』(東京農業大学出版会、共著)、教育情報誌『たのしい学校』(大日本図書・連載中)など。

- 清水 晃
- 東京都立大学・(一財)進化生物学研究所 客員研究員、理学博士
- 東京都立大学(理学研究科生命科学専攻)を定年退職後、東京都立大学・(一財)進化生物学研究所の客員研究員となり、ハチ類、特にクモバチ科の分類、生態、行動、系統、進化などの研究を継続。
著書:『新訂 原色日本昆虫大図鑑』(北隆館、共著)、『日本産有剣ハチ類図鑑』(東海大学出版部、共著)、『日本昆虫目録』(日本昆虫学会、櫂歌書房、共著)、「寄生バチと狩りバチの不思議な世界」(一色出版、共著)、『ハチとアリの自然史』(北海道大学図書刊行会、共著)など。

